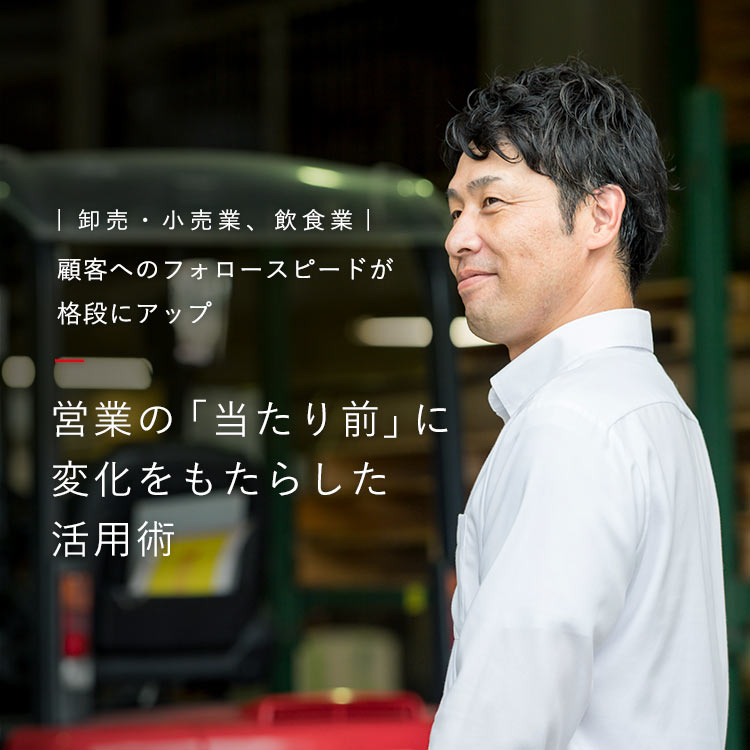
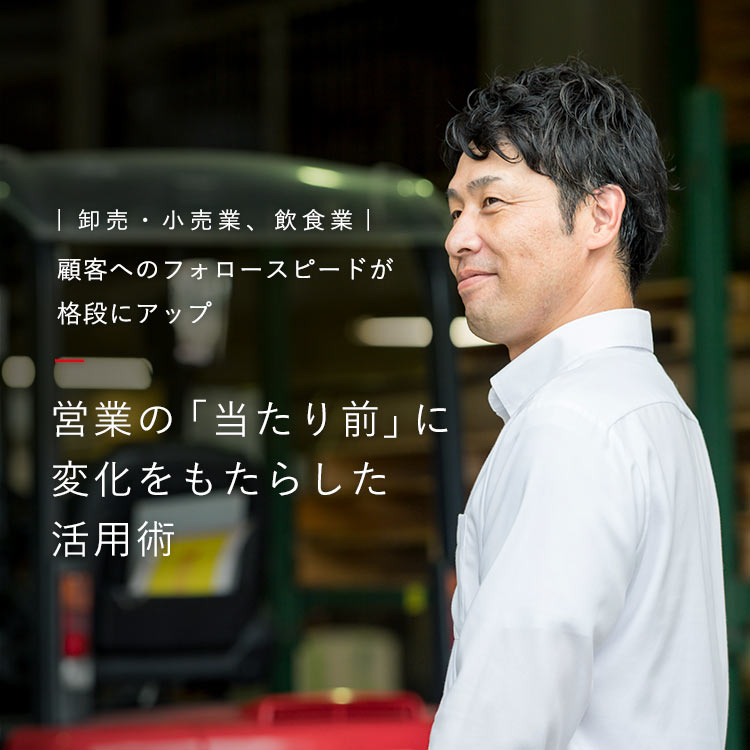


弊社は1964年の創業以来、物流に関するあらゆる業務に携わってきました。各分野を専門的に担うグループ会社とも連携し、物流業務のトータルソリューションを提供しています。
もともと私も一営業として梱包、倉庫、物流サービスの営業を経験してきました。当時のスタイルはアナログで場当たり的な飛び込み営業でした。とにかく、行動。戦略を立ててロジカルに動くのではなく、人海戦術で個人プレイが多く、一方的に課された数字も根拠がないものでした。属人性の非常に高い営業スタイルに、私自身課題感を感じていましたし、これを変えられないことに、もどかしさも同時に感じていましたね。
転機は機器設備の販売に特化した物流企画課に配属されたことでした。減産に強い危機感を経営者層がもっていて、「単なる物売り」から「お客様の課題解決をできる存在」を目指すべく、新しいビジネスを創造するプロジェクトが立ち上がり、そのメンバーの取りまとめ役として私が任命されたのです。
まずはメンバーで「いかにお客さまの生産性を上げるのか?」「それを実現するために私たちに何ができるのか?」をテーマにしたアイデア出しを行いました。さまざまな意見が出ましたが、「自社の営業生産性を向上させれば、お客様の生産性も上がり、ひいては業績もアップできるのではないか」という結論にいたりました。それが、最初のスタートでした。


経営層やプロジェクトメンバーでは改革を進めるためのムーブメントが少しずつ起こりはじめていたのですが、営業の現場では相変わらず個人プレイで属人的な営業活動が行われていました。隣のチームの動きはもちろん、同じチームのメンバーの動きもわからず、自分自身が持っている情報だけを頼りに日々営業活動をしていたのです。営業は外出の際に名刺ファイルを持ち歩いており、他の営業がすでに訪問をした企業に再訪してしまうというバッティングもしばしば起こっていました。
そんな状況を、Sansanで打破できるかもしれないと考えたことも、Sansan導入の決め手の一つです。

ただ、アナログな企業文化である当社では、導入された後も営業が名刺を取り込んでくれないといった問題がありました。せっかく新しいツールを導入しても、実際に活用できなければ意味がありません。そこで、まずは「習慣化」に取り組みました。
名刺の取り込みを習慣化するためには、その意義を知ってもらう必要があります。一人ひとりに、Sansanで名刺を取り込むことで得られるメリットを伝え、まずは名刺を取り込んでもらうよう根気強く説得に回りました。また、名刺を取り込んだらポイントを加算し、それが評価につながるという制度を導入しました。口頭で意義を伝え続けながら、仕組みを整える。そうやって、当初は抵抗をもっていた人も「いつでもデータが見られて便利だね」という考え方に変わり、名刺の取込みも定着していきました。
Sansanを導入した後は、確実に営業効率がアップしたと実感しています。以前は全体で月でも数件ほど発生していた営業間のバッティングも、今では0近くに。外出先でアプリを使えばいつでも情報を見られるので、名刺ファイルを持ち歩く必要もなくなりました。


もう1つ、営業間の情報共有のために活用している機能として「コンタクト」が挙げられます。名刺の取り込みを定着させたあとの第二フェーズとして、コンタクト機能の活用に取り掛かりました。
ここで意識したポイントは2つ。取込と同様に、実施するメリットを伝えるということと、実際に利用するメンバーが使いやすいものにできるかどうかです。後者については、まずは中間管理職を交えて必要な項目をピックアップして、スムーズに記入してもらうためのフォーマットを作成し、各部署で運用を開始してもらうという方向性で進めました。コンタクトは自社に合わせたカスタマイズができるからこそ、定着させるために現場の使いやすい運用を考えるという点を意識しましたね。
すっかり定着した今ではコンタクトも期待通りの効果があったと実感しています。まずはコンタクト(日報)記入後のフォロースピードです。以前は紙で日報を提出していたので、出張等で支店に上司がいない場合は、もちろん確認やフィードバックも遅れ、顧客へのフォローが数日後になるということもよくありました。それがいつどこにいてもSansan上でやりとりできるようになったため、その後のフォロースピードは格段に上がりました。
また、社内での情報共有の工数も減りました。それまで進捗状況について共有する際は都度ミーティングか、社内メールを使用していましたが、Sansanのメッセージに置き換えました。コンタクトとそれに関するやりとりも全てSansan上に記録されるので、「この件どうなってる?」というやりとりも、今では「Sansan見といて」で済ませられるようになりました。
顧客へのフォロースピードUPと日々の業務の工数削減。これによりお客さまの満足度もアップし、実際に売上もUPしています。

Sansanの定着には時間が掛かった当社でしたが、焦らず段階的に進めることにより、今ではなくてはならないツールとなりました。
印象的なエピソードとして、今まではSansanを導入する過程で、企業文化が変わることに多少の反発もあった営業から、自発的にSansanを活用した施策が発案されたことがあります。私も知らない間に、自然に動いていたので驚きました(笑)。
具体的には、多地域に拠点をもっていて、複数の営業が担当している「広域顧客」の可視化です。例えば、取引先の拠点情報を調べ、その拠点ごとに当社との繋がりがどれくらいあるかSansanで調べる。繋がりが薄い拠点があれば、繋がりの強い拠点の担当者に紹介依頼をする。これまで営業担当同士の線引が曖昧で対応が難しく、手をつけにくい領域だったのですが、人脈の可視化やコンタクト機能を駆使することで、新たな営業スタイルが創出されました。営業同士の情報共有も密になったので、今後は営業エリアを拡大して、より広域顧客に対するアプローチも強化していきたいと考えています。
アナログからデジタルに。個人プレイからチームプレイへ。“当たり前”が大きく変わり、Sansanの導入は成功したと考えています。
今後はデータを活用して戦略を立て、さらに攻めの施策に結びつけていきたいと考えています。これからは案件管理の試験運用もスタートします。こちらも試行錯誤することになるかと思いますが、全社に根付くようにしたいですね。
素敵な笑顔と柔らかな物腰でお話くださった乾様。同僚の方曰く、社内でSansanの利用を促進される際はまた違う顔があるとのことです。アメとムチの使い分けも利用定着のコツなのかもしれません。次は案件管理機能からどのような効果が生まれるのか、今からとても楽しみです。
カスタマーサクセス部 木村
